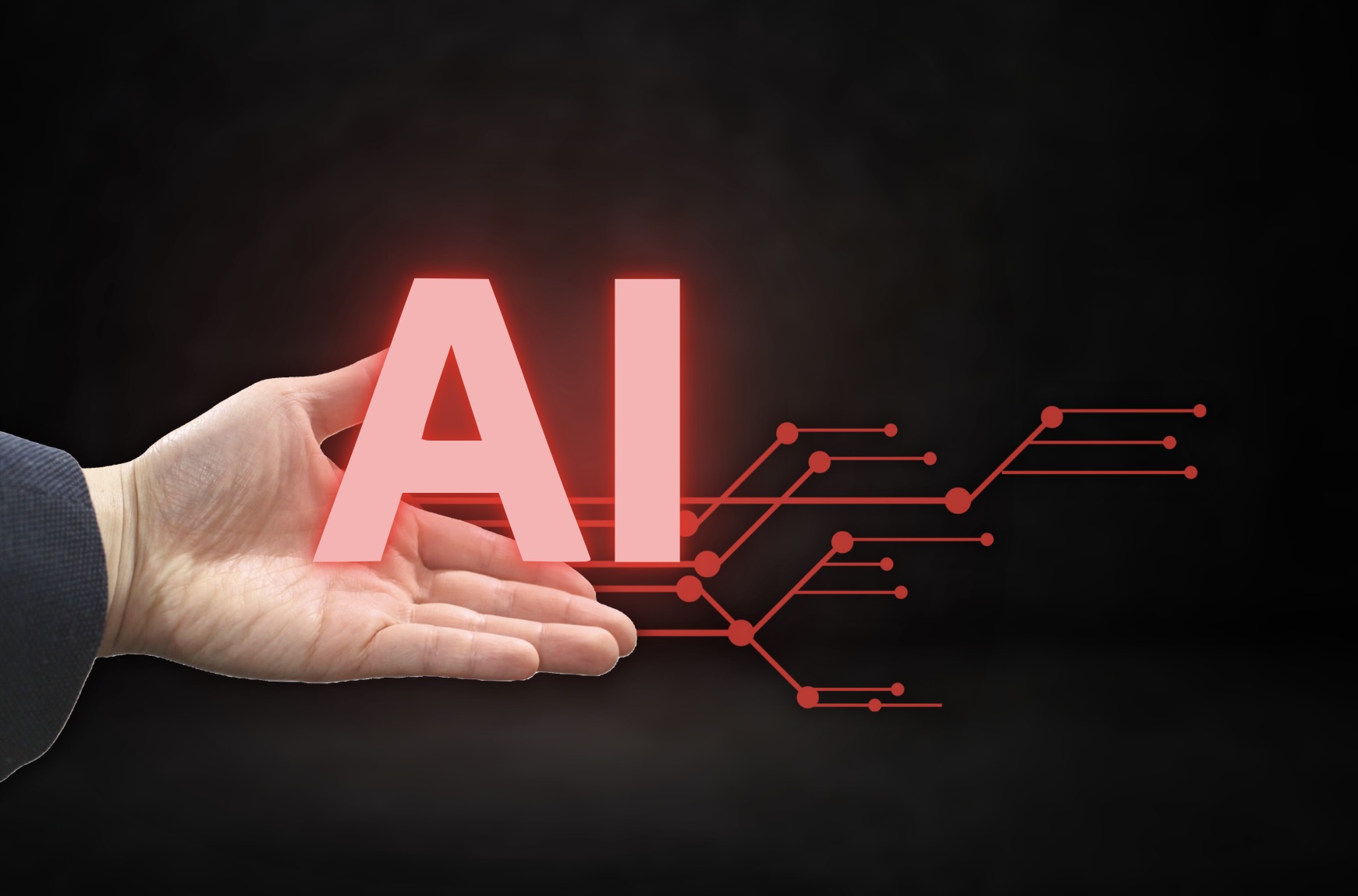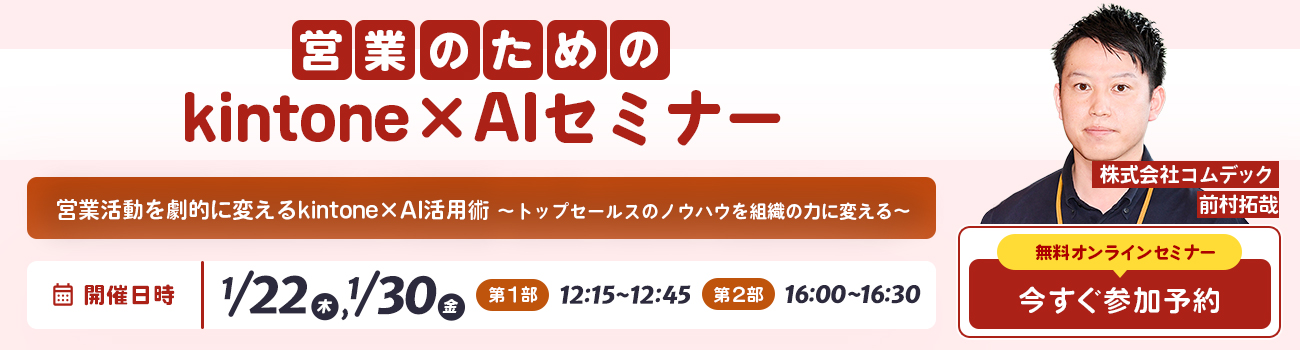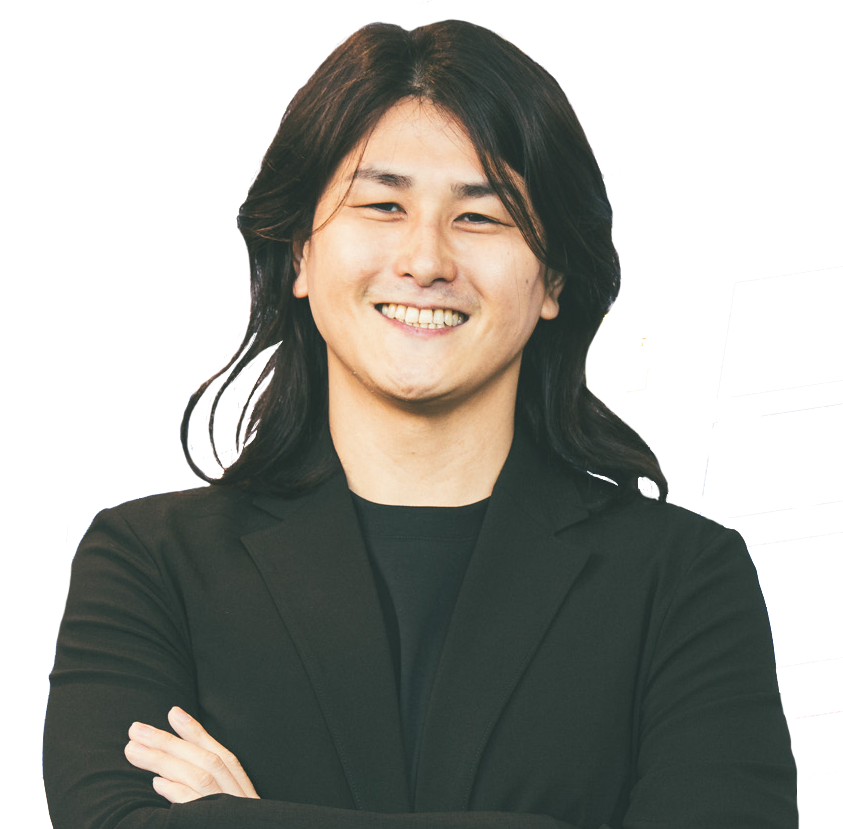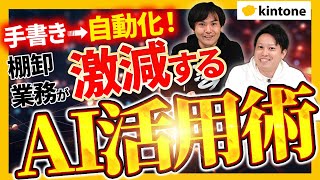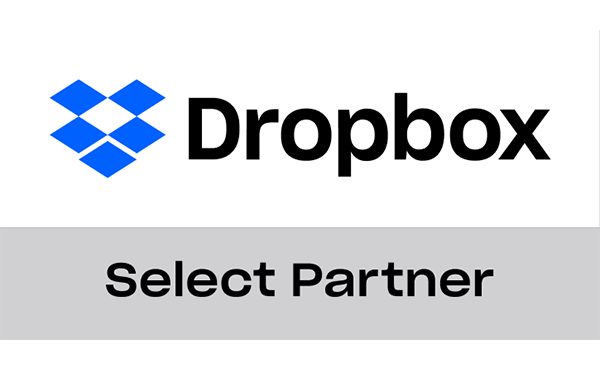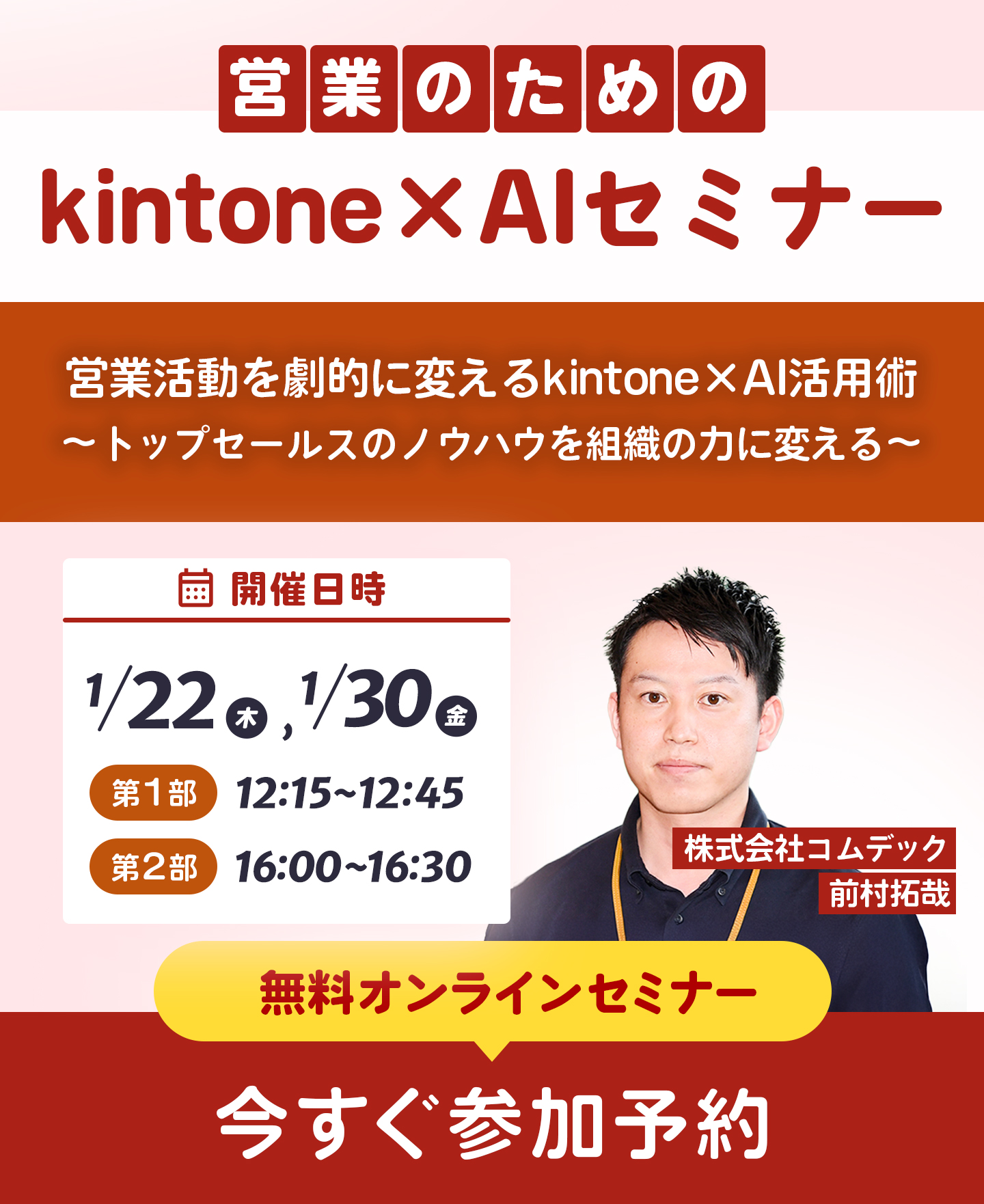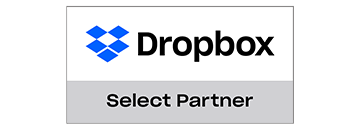AIによるデータ活用とは?具体例や成功のポイントも解説
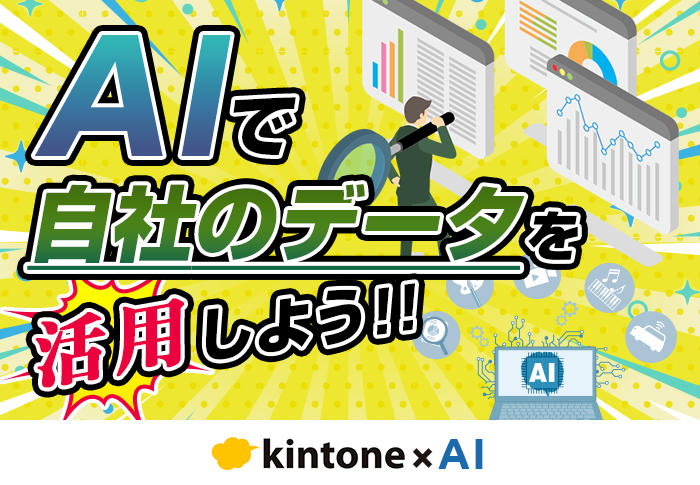
近年、企業が取り扱うデータ量は急激に増加しており、それらをどう活かすかが競争力にも影響を及ぼすようになってきました。
一方で、人手不足によって「どうデータを活用すると自社がより良くなるのか」を検討する時間がなく、思うようにデータ活用が進んでいないという企業さまも多いのではないでしょうか。
そんなときにAIを導入すれば、高度な分析や予測が瞬時にできるようになり、経営判断や業務改善に役立ちます。
本記事では、AIによるデータ活用の基礎知識や成功のポイント、導入事例を解説します。
AIを業務に使いたいと考えている方、蓄積されたデータを活かしたいと考えている方は是非ご覧ください!
この記事でわかること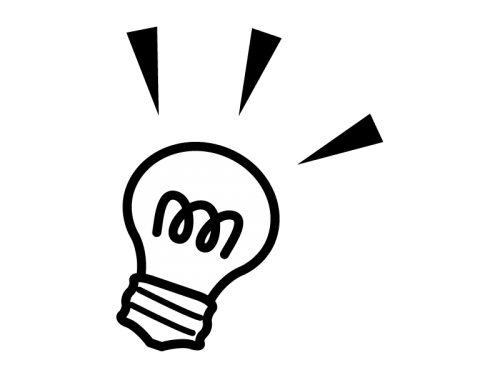
- AIによるデータ活用でできること
- データ活用にAIを導入するメリット
- AIによるデータ活用を成功させるポイント
![]() こんな人におすすめの記事です
こんな人におすすめの記事です
- AIでどのようなデータ活用ができるのか知りたい方
- どうすればAIでうまくデータ活用ができるか知りたい方
目次
AIによるデータ活用の基礎知識
データ活用にAIを導入すれば、これまで扱いきれなかった膨大な情報を短時間で処理できるようになり、より柔軟かつ精度の高い分析を行えます。
これらを可能にしているのが、AIを構成する「機械学習」や「ディープラーニング」という技術です。
機械学習は、大量のデータを用いてAIがルールやパターンを学び、予測や分類の精度を高めていく技術を指します。
また、ディープラーニングは機械学習の一種で、人間の脳の神経回路を模したニューラルネットワークを用いてAIが自律的に特徴を抽出し学習する手法です。
特にディープラーニングは、音声認識や画像解析、自然言語処理といった高度な分野で成果を上げており、非構造化データの解析にも強みを発揮します。
こうした技術のおかげで、AIによるデータ活用は人の手では到底追いつかないスピードと精度を実現し、新たな価値を創出しています。
AIによるデータ活用でできること
AIによるデータ活用は、営業や製造、物流、医療などあらゆる分野で成果をあげています。
例えば営業やマーケティングの分野では、顧客データや購買履歴、WEBのアクセスログをもとに、顧客一人ひとりに最適な提案や情報提供を行うことが可能です。
小売や物流であれば、過去の販売実績や季節要因、イベント情報などをAIが分析し、需要を高精度で予測できます。
これにより、在庫の過不足を防ぎ、廃棄ロスや欠品リスクを最小限に抑えられるのがメリットです。
製造業では、検査結果や稼働データをもとに、設備が故障する予兆を検知し、計画的なメンテナンスを実施することで生産ラインの停止を防げます。
医療やヘルスケア分野では、患者データや過去の診断履歴、検査結果などをAIが解析し、医師の診断をサポートしたり、疾患の傾向を分析したりできます。
ここで挙げた例のように、AI活用は単なる業務効率化にとどまらず、ビジネスモデルそのものの変革や新たなサービス創出にもつながっているのです。
データ活用にAIを導入するメリット
データ活用にAIを導入すると、次のようなメリットが得られます。
分析や予測の精度向上
AIを導入すると、人間では処理しきれない膨大な量のデータをリアルタイムで解析し、精度の高い分析や予測を行えることがメリットです。
従来はサンプルデータや過去の統計情報をもとにした限定的な分析が主流でしたが、AIを用いることで、数百万件規模のデータや非構造化データも瞬時に処理できます。
その結果、売上予測や需要予測、リスク予測などの精度が大幅に向上し、より正確な事業戦略の立案が可能になります。
また、人間が関与しないため作業スピードが格段に早く、人的ミスを回避できることもメリットです。
客観的なデータに基づく意思決定の実現
経営判断や業務方針の決定において、従来は担当者の経験や勘に頼る部分もありました。
しかしAIを活用すれば、膨大なデータを基にした客観的かつ定量的な分析結果を提示できるため、判断のブレを最小限に抑えられます。
これにより、根拠のある戦略立案や施策実行が可能になり、社内外からの信頼性も向上するのがメリットです。
業務効率化と人手不足の解消
AIを活用することで定型的で繰り返しの多い業務を自動化できるため、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。
例えば、データ入力や集計、レポート作成といった時間のかかる事務作業をAIに任せれば、作業時間が大幅に短縮されます。
これにより、従業員はより戦略的な判断やクリエイティブな業務に時間を割けるようになり、組織全体の生産性を向上させられることもメリットです。
AIの導入手順とデータ活用を成功させるためのポイント
データ活用にAIを導入する流れは、以下の通りです。
- 課題とゴールの設定
- データ収集
- データクレンジング
- AIによるデータ分析
- 施策の決定
- 実行
- 効果測定・改善
AIは全てを解決してくれる魔法の道具ではないため、何をしたいか、そのために何が必要か、どうすればもっと良くなるか、といったことを考えながら使っていくことが重要です。
次に挙げる3つのポイントを意識してPDCAサイクルを継続的に回すことで、AI活用は進化し続け、企業の競争力向上につながります。
課題とゴールを明確に設定する
まずは、解決したい課題やゴールをはっきりさせることが大切です。
ゴールが曖昧なままでは分析の方向性が定まらず、得られる結果も活用しづらくなります。
例えば、営業部門であれば「成約率を10%向上させるために、AIで顧客の購買確率を予測する」のように、定量的な目標を設定すると成果を測定しやすくなり、導入後の改善もスムーズに進みます。
きれいなデータベースを用意する
AIの分析精度は、投入するデータの質に大きく依存するのが特徴です。
誤入力や表記ゆれ、欠損値、重複データなどが多いと、AIは誤った学習をしてしまい、精度の低い予測結果を出す恐れがあります。
そのため、分析前には必ずデータクレンジングを行い、正確かつ一貫性のあるデータベースを構築することで、AIのパフォーマンスは飛躍的に向上します。
データ人材を確保する
AI活用を成功させるには、データを適切に扱える人材も欠かせません。
データサイエンティストやAIエンジニアはもちろん、業務知識とデータ分析の両方を理解している担当者がいると、プロジェクトは格段にスムーズに進みます。
自社でこうした人材を確保するのが難しい場合は、外部の専門家やコンサルタントと連携するのも有効な方法です。
プロの力も借りつつ、社内研修やトレーニングを実施し、データリテラシーを底上げする体制を作っていきましょう。
AIでのデータ活用ならkintoneがおすすめ
AIによるデータ活用を進めたい場合は、「kintone(キントーン)」との連携がおすすめです。
kintoneはサイボウズが提供するクラウドシステムで、プログラミングの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリをノーコードで構築できます。
案件管理や顧客管理、在庫管理など、あらゆる業務データを一元的に蓄積・構造化できるため、AI活用のためのデータ基盤として非常に有用です。
また、APIを活用すれば外部サービスやAIツールとも連携できるため、データの自動収集や分析結果の反映もスムーズに行えます。
kintoneの活用事例については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
▼kintone(キントーン)とは?できること・できないことまとめ アプリの活用事例もご紹介!
なお、kintoneとAIを連携させる際には「kintone for 生成AI」の活用がおすすめです。
kintone for 生成AIは、複数のkintoneアプリに蓄積されたデータを横断的に抽出・分析できるほか、会議や商談の記録から議事録を自動作成したり、日報や報告書をメモ入力から整形して登録したりと、幅広いデータ活用に対応できます。
専門知識がなくても導入しやすく、既存の業務フローに自然に組み込める点も大きな特長で、効率化と判断の迅速化を同時に実現します。
【事例】介護業でkintoneとAIを連携して、活動記録から報告資料を自動生成
ここでは、実際にkintone for 生成AIでkintoneとAIを連携して、データ活用に成功した事例を紹介します。
株式会社ワンセルフさまは、群馬県で10の障害者福祉施設を運営する企業さまです。
以前は、利用者さまの活動記録や面談記録を紙の書類やエクセルで管理されていたため、面談資料を作成する際には半年分の記録を紙で印刷してマーカーでチェックしたり、担当スタッフに聞き取りをしたりと、1人分の作成に1時間以上の時間を要していたそうです。
そこで株式会社ワンセルフさまでは、資料作成の時間を短縮するために、利用者情報や活動記録のデータ管理をkintoneアプリに集約してChatGPTと連携。
活動記録の要約をAIに任せたことで、わずか3分ほどで面談資料の原案を作れるようになり、スタッフは内容の確認と微調整をするだけで面談資料が完成するようになりました。
これにより、事務作業にかける時間が大幅に短縮でき、スタッフは利用者さまのケアにより集中できる環境を実現しています。
▼kintoneとChatGPTを連携して介護記録に基づく資料作成を効率化|介護福祉事業 株式会社ワンセルフさまの開発事例
AIによるデータ活用ならコムデックにお任せください
さまざまなITツールの普及で、データの蓄積は簡単になってきましたが、蓄積したデータを活用しきれていない企業さまも多いのが実情です。
AIによるデータ活用は、一度仕組みを構築してしまえば、あとは最小限の手間で運用できますので、ぜひ導入を検討されてはいかがでしょうか。
コムデックでは、kintone × AI 活用をサポートする「kintone × AI 事例集」を提供しております。
お客さまの課題や業務フローに合った事例を豊富に紹介していますので、ぜひご覧ください。