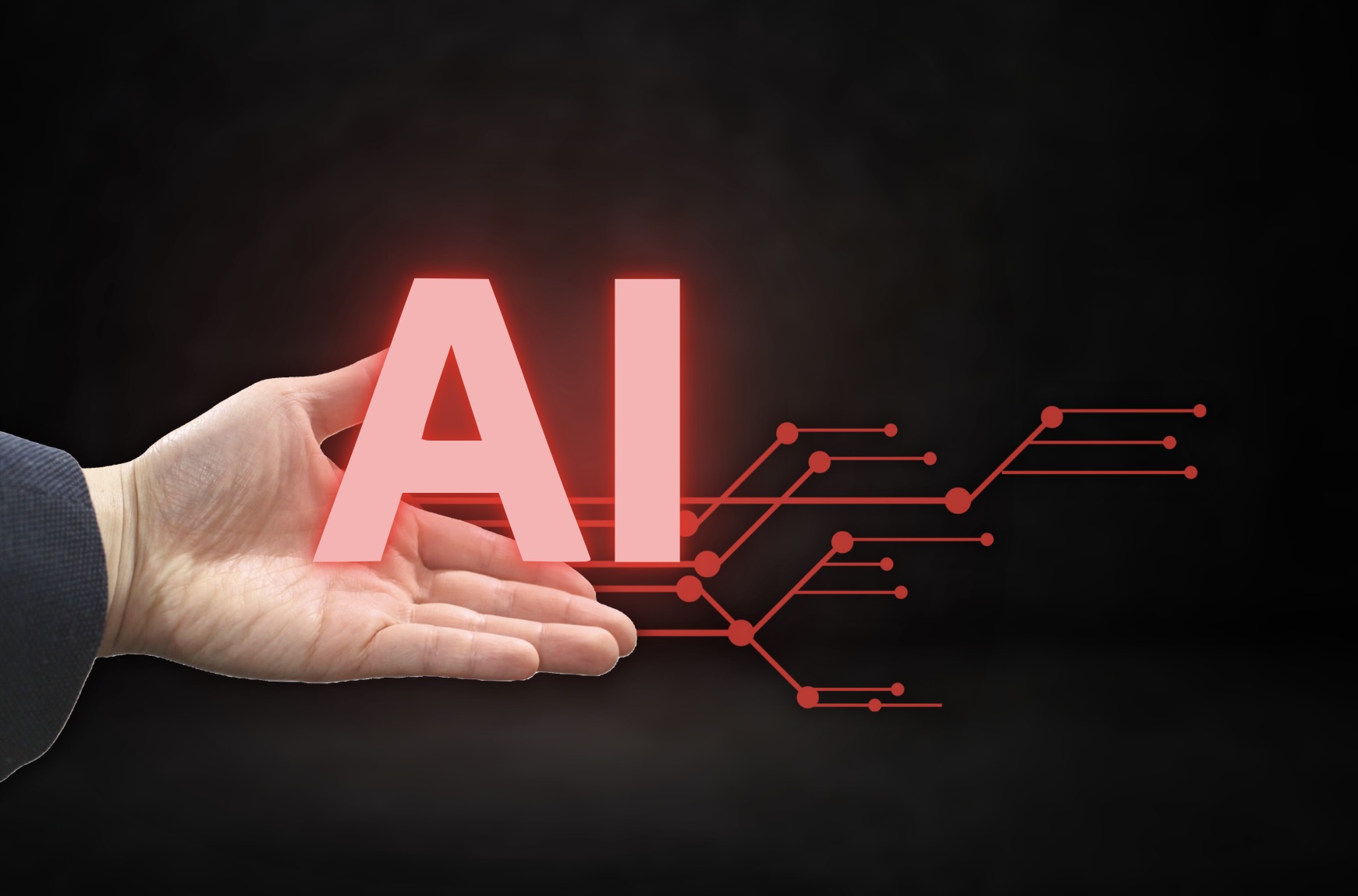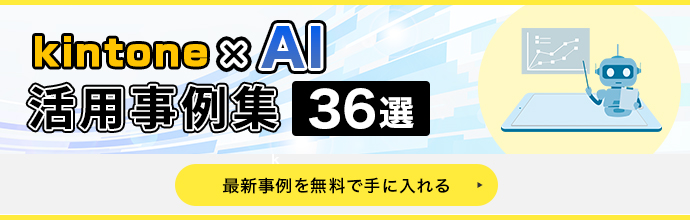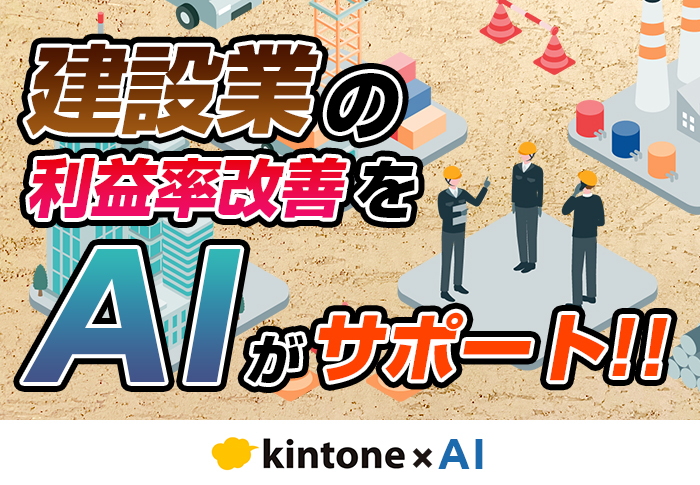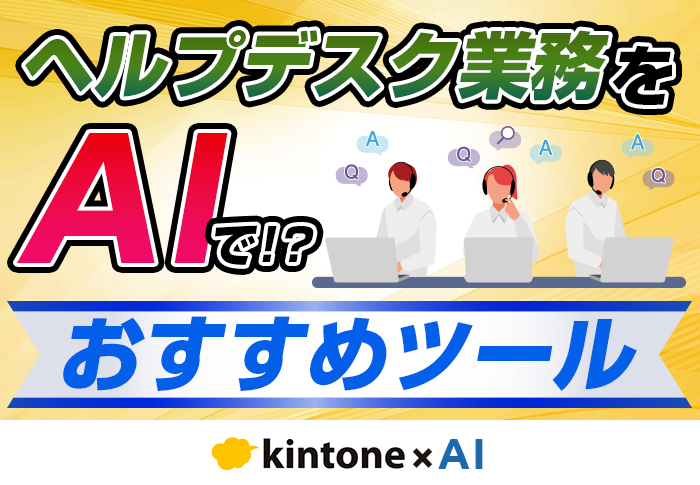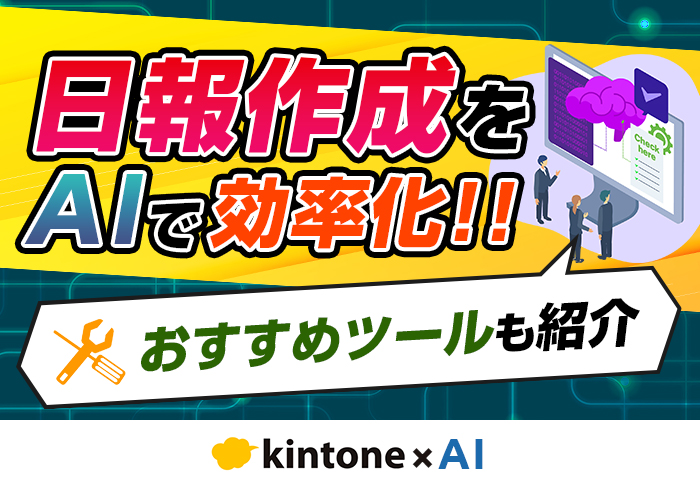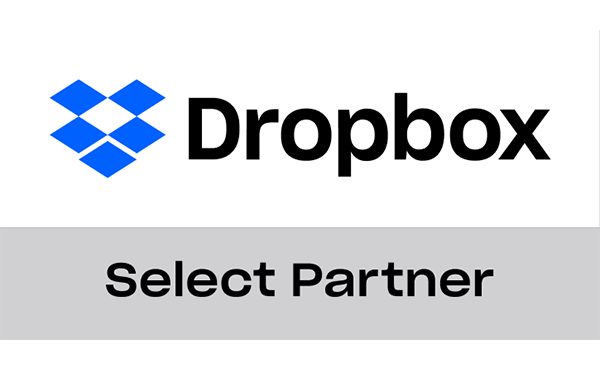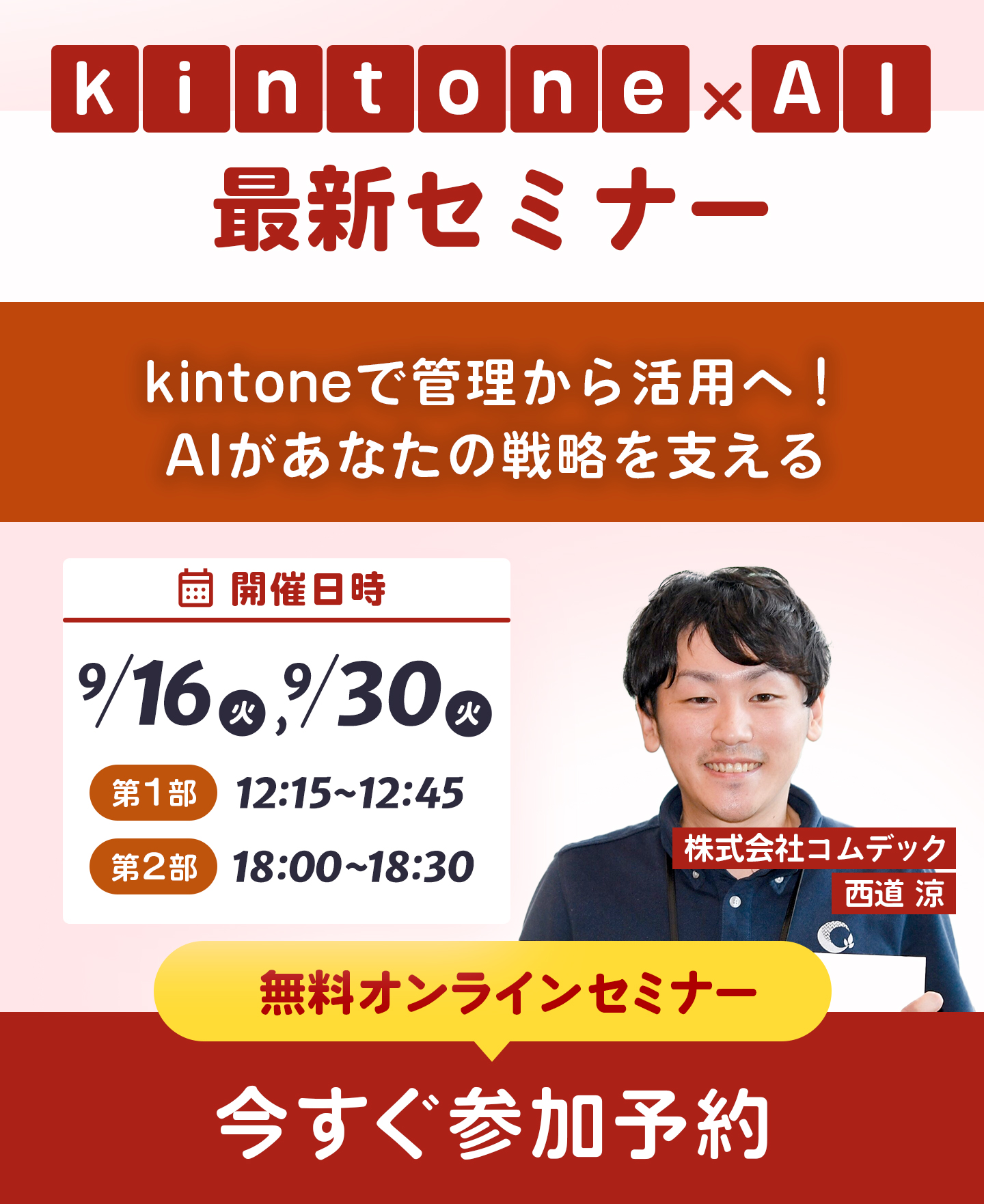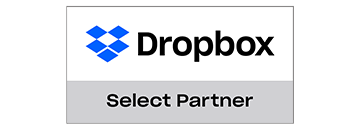データ入力をAIで自動化!おすすめツール・導入時のポイントを解説

単純作業の代表ともいえるデータ入力は、多くの企業で時間やコストを無駄にする一因となっています。
「やるべき仕事がたくさんあって、入力作業なんてやっている場合じゃないのに……」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
こうした課題に対応する手段として、AIを活用した入力の自動化が注目されています。
本記事では、データ入力におけるAI活用のメリットや注意点、おすすめの活用分野などを詳しく解説します。
データ入力作業を削減したい方や、業務にAIを活用したい方は是非ご覧ください!
この記事でわかること
- データ入力でAIを活用するメリット
- AI活用に適したデータ入力業務
- データ入力にAIを導入する際のポイント
 こんな人におすすめの記事です
こんな人におすすめの記事です
- データ入力をAI活用で効率化したい方
- 具体的にどんな業務でAIが使えるのかを知りたい方
目次
データ入力業務によくある課題
データ入力は、大きく分けると手書き文字の読み取り、印刷物のデジタル化、WEBからの情報収集、音声データの文字起こしの4種類があります。
どの種類のデータ入力作業にも共通する課題として、作業に時間がかかることや、作業者のスキルによって正確性・スピードに差が出ることなどが挙げられます。
また、データのフォーマットがバラバラな場合は人の目で確認しなければならず、それがさらなる負担となります。
年度末や繁忙期など特定の期間に作業が集中することも多いのが特徴ですが、簡単に人員を増やすこともできず、納期や品質に支障をきたすケースも見られます。
データ入力にAIを導入するメリット
上記のような課題の解決策として、AIの導入はとても有効な手段です。
AIは、ルールに従って処理を行うRPAとは異なり、機械学習によりデータの意味を理解したり、形式の異なるデータを自動で補正したりできるのが特徴です。
ここでは、AIを使ったデータ入力のメリットを解説します。
作業時間の短縮
データ入力にAIを導入する最大のメリットが、作業時間の短縮です。
従来の手入力では、膨大な時間をかけて一件ずつ確認・入力する必要がありましたが、AIなら一括で高速処理できます。
さらに、AIは24時間365日稼働できるため、業務時間外や休日でもデータ処理を進められます。
こうした効率化により、浮いた時間は分析や改善など、より付加価値の高い業務に充てられるようになるでしょう。
人為的ミスの削減とデータ品質の安定
人の手によるデータ入力には、どうしても人為的なミスがつきものです。
入力漏れ、誤字脱字、転記ミスなど、一つ一つは小さなミスでも、最終的に大きなトラブルや再チェック、そもそもの作業のやり直しにつながることもあります。
AIを活用すれば、こうした人為的ミスを最小限に抑えられるのがメリットです。
人間のように担当者やその日の調子によって品質が変わることも無いため、データの正確性と一貫性を保てます。
コスト削減
AIの導入は、長期的に見るとコスト削減にもつながります。
これまでは、繁忙期に外注やアルバイトを活用する企業も多く、残業代や採用コストがかさんでいました。
外注の場合は、作業量が少ないと引き受けてもらえなかったり、割高になったりするケースもあったでしょう。
その点、AIなら残業代や退職の心配もなく、一定のコストで安定して稼働し続けてくれることがメリットです。
AIによるデータ入力が適した業務
AIによるデータ入力が適している代表的な業務には、次のようなものがあります。
顧客管理
顧客管理業務においては、申込書や契約書、アンケートなど、紙媒体からのデータ入力が多いのが特徴です。
AIを活用することで、紙の書類から必要な情報を正確に抽出し、システムへの自動登録が可能になります。
OCR(光学文字認識)と連携したAIであれば手書き文字も読み取れるため、工数を大幅に削減できるでしょう。
経理
経理部門では、請求書や経費精算書といった定型フォーマットの書類を扱う機会が多いのが特徴です。
AIを使えば、これらの書類に記載された日付、金額、取引先名などを正確に読み取り、仕訳データとして自動的にシステムに反映できます。
これにより、作業スピードの向上だけでなく、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
総務人事
総務人事部門では、履歴書の入力、勤怠管理、給与計算などでAIが活用できます。
特に、給与データや人事評価、健康診断結果などの情報は機密性が高いため、入力作業を誰にでも頼むわけにはいきません。
その点AIツールは、セキュリティ対策さえきちんとなされていれば、プライバシーの面でも安心してデータ入力を任せられます。
データ入力におけるAI活用事例
ここからは、データ入力におけるAI活用事例を2つ紹介します。
いずれも、業務管理アプリとして有名な「kintone(キントーン)」と連携して活用した事例です。
kintoneは、プログラミングの知識がなくても簡単にアプリを構築・カスタマイズでき、さまざまな外部システムとも連携できるため、AIとの相性も良いツールです。
kintoneを使ってできることや活用事例については、こちらの記事で詳しく紹介していますのであわせてご覧ください。
▼kintone(キントーン)とは?できること・できないことまとめ アプリの活用事例もご紹介!
AI-OCRとkintoneを連携して紙ベースの情報を集約
OCRは、紙に書かれた文字をスキャンして、編集可能なデジタルデータに変換する技術です。
従来のOCRでは、決まったレイアウトやフォントにしか対応できませんでしたが、最近はAIを搭載したAI-OCRによってあらゆる書類に対応できるようになってきました。
そのため、名刺や契約書はもちろんのこと、手書きの申込書や問診票、アンケートなどにも対応可能です。
kintoneと連携させれば、それぞれの書類から名前や日付、金額、コメントなどを読み取って、kintoneアプリの入力項目に自動で登録してくれます。
AIは使うたびに学習を重ねるため、精度がどんどん向上していくこともメリットです。
例えば紙やFAX、メールで届いた請求書や発注書をOCRで読み取ってkintoneに登録すれば、発注管理や原価管理がもっとやりやすくなるでしょう。
こちらの記事では、kintoneとの連携におすすめのツールについても詳しく紹介しています。
▼kintoneとAI-OCR を連携できるプラグイン5選!活用シーンやメリットも解説
ChatGPTとkintoneを連携して請求書のデータ入力を効率化
ChatGPTとkintoneを連携すると、請求書のデータ入力も自動化できます。
請求書と言えば、発行元によってフォーマットや明細の書き方が異なるのが特徴です。
これまでは、人の目で見て判断せざるを得ませんでしたが、画像としてChatGPTに読み込ませることで、どこに何が書かれているのかの判別も自動化できます。
AI-OCRの専用ツールに比べれば精度は多少劣る部分もありますが、一から人の手で入力するのに比べれば大幅な効率化につながります。
ChatGPTであれば、特別な機器を導入することなく、今あるパソコンとスキャナだけで実装できるのがメリットです。
ChatGPTを使った事例については、こちらの動画で実際の操作画面とともに詳しく解説しています。
データ入力にAIを導入する際のポイント
データ入力へのAI導入を成功させるためには、大きく3つのポイントがあります。
業務フローを整理する
まずは、現在の業務フローを可視化し、どの工程が自動化に適しているかを見極めることが重要です。
いきなりすべての業務をAIに置き換えようとするのではなく、部分的に始めて、効果を測定しながら段階的に拡大していきましょう。
現場の社員にも、AI導入の目的や全体像を共有しながら進めていくのがおすすめです。
自社に適したツールを選ぶ
AIツールにはさまざまな種類があり、それぞれに強みや特性があります。
導入を成功させるには、自社の業務に最適なツールを選ぶことが不可欠です。
ツールを選ぶ際は、料金はもちろんのこと、AIの精度やセキュリティ、サポート体制などもしっかりチェックしましょう。
可能であれば、無料トライアルやデモンストレーションを活用して、実際の使用感を確認するのがおすすめです。
必ず人の目でチェックをする
AIの精度は近年飛躍的に向上していますが、それでも100%の正確性を保証するものではありません。
特に、手書き文字や音声データでは誤認識が起きることもあります。
そのため、AIによる自動処理の後には、必ず人の目で内容を確認し、必要に応じて修正する工程を残しておくことが重要です。
AIを使ったデータ入力のことならコムデックにお任せください
AIによるデータ入力の自動化は、業務効率の向上やコスト削減の強い味方ですが、導入には業務理解やツール選びなど専門的な知見が不可欠です。
コムデックでは、AI 活用をサポートする「AI伴走支援サービス」を提供しております。
データ入力に限らず、分析業務や顧客対応など、あらゆるシーンでのAI活用をお手伝いしております。
お客さまの業務課題に合わせて、最適な連携ツールや設定方法をご提案しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。