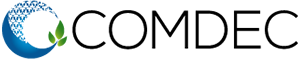お客様インタビュー
INTERVIEW
作られたアプリに合わせるんじゃなく、自分たちの働き方に合うアプリを一緒に作りたい
株式会社松村製作所さま
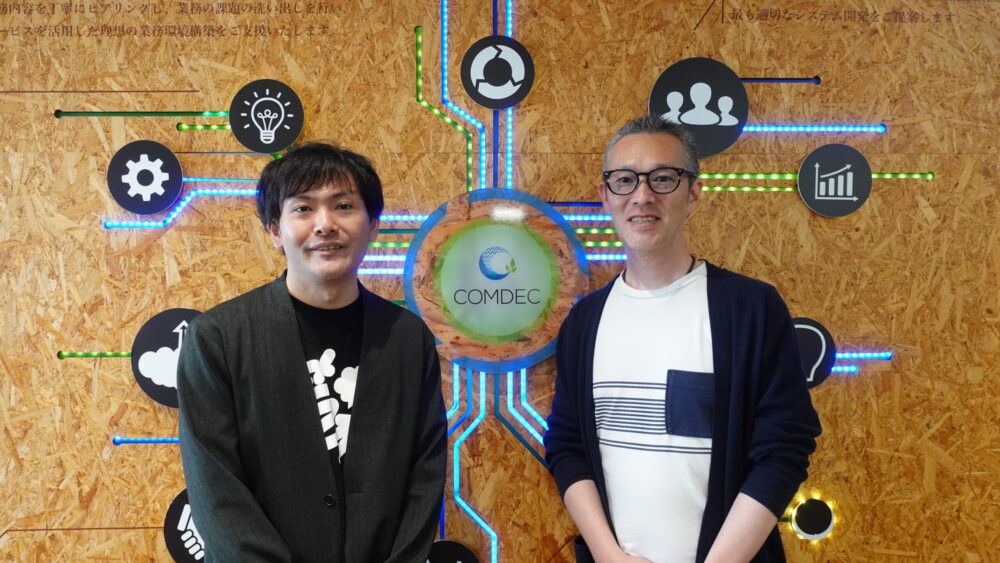
| 掲載日 | 2025.07.30 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 |
| 利用規模 | 1〜49人 |
| 業種 | 製造業 |
| 導入ソフト | kintone |
| HP | http://www.matsu-ss.co.jp/index.html |

株式会社松村製作所
1959年創業の株式会社松村製作所さまは、創業以来鉄道インフラ設備の板金加工を主に事業活動を展開していらっしゃいます。
『創ろうよ、「こだわり」を』の理念のもと、価値ある製品を創造し、社員が明るく働きやすい環境作りを日々積極的に取り組んでいるのが特徴です。
| 目的 | ・社内の情報共有や業務進捗の見える化を行いたい。 ・受注管理から請求管理までをシームレスに行いたい。 ・もともとAccess ペーパーレスやアナログ管理の脱却。 |
|---|---|
| 課題 | ・情報や仕事の流れを共有出来ず、確認作業や段取りに時間が掛かっていた。 ・受注管理と見積が別ソフトで管理に時間が掛かっていた。 ・図面や品質管理資料など、膨大な紙ファイルを管理・保管が大変。 |
| 効果 | ・現場にモニターを設置し情報共有・進捗管理が出来るようになった。 ・受注から請求までの一元管理が行えるようになった。 ・アプリで管理、必要な場合にすぐ呼び出すことが可能になった。 |
同じ目線で一緒にアプリを作ってくれる、コムデックの伴走支援とは?
お話を伺った方:代表取締役社長 松村功様
Accessと紙の帳票はそろそろ限界だと思っていました
事業内容
当社は1959年に創業し、現在は東京都昭島市に本社を置く板金加工業者です。
主に、踏切で使われる警報灯や駅の行先案内表示板などを製造し、60年以上にわたり鉄道インフラを支えてきました。
『創ろうよ、「こだわり」を』という理念のもと、時代のニーズにお応えして価値ある製品を作れるよう、社員一丸となって業務に取り組んでいます。
kintone活用の目的と当時の課題
弊社ではこれまで、受注管理や進捗管理はMicrosoft Accessでデータベースを作成し、紙の帳票を印刷して使っていました。
しかし、この方法では情報や仕事の流れを共有しにくく、確認作業や段取りに時間がかかることが課題でした。
受注管理と見積管理が別のソフトになっていたため、余計な手間もかかります。
また、図面や品質管理などの膨大な資料を紙ファイルで管理しており、場所を取ることや探しにくいことも悩みの種でした。
そんな中、とある同業の社長さんから「kintoneがいいよ」という話を聞きました。
確かにkintoneなら今の課題を解決できそうだということで、次の3つのことを目的に、導入することを決めました。
1つめは社内の情報や進捗状況を見える化すること、2つめは受注管理から請求管理までをシームレスに行うこと。
そして3つめはアナログ管理の脱却とペーパーレス化です。
日常業務の延長にkintoneを置くのが、一番難しかったですね
コムデックを選んだ理由を教えてください
実は、kintoneの導入を決めてからコムデックさんにたどり着くまでには、いろいろな経緯がありました。
最初は、とある大手システム業者さんに頼もうと思ったのですが、これはうまくいかずに終わりました。
というのも、私はTISの無料プラグインを使いたかったのですが、有料のプラグインを入れないとできない、と言われてしまったんですよね。
こちらがやりたいことを話しても、あまり理解してもらえませんでした。
そこで、もう一度ネットや動画を調べているうちにコムデックさんの「kintone芸人」を見つけたんです。
最初は、生田社長のことを本物の芸人さんだと思って見ていました。笑
コムデックさんの解説動画も分かりやすいし、同じ目線でサポートしてもらえそうだなと感じたのが決め手です。
あとは、これから自分たちがkintoneを活用していくにあたって、モチベーションとかワクワク感も大事だと思っていて。
そういう意味で、生田社長が動画やXで楽しい発信をされていたことも大きかったですね。
コムデックさんなら、作られたアプリにこちらが合わせるのではなく、同じ目線で一緒に作ってもらえそうだなと思いました。
IT化が急速に進んでいる秘訣があれば教えてください
他社のスピード感は分かりませんが、「IT化が速い」と言ってもらえて嬉しく思います。
秘訣があるとすれば、社員が協力してくれていることが一番ですね。
これには、私も本当に感謝しています。
改善すべき課題が見える化して、社員たちも納得のうえで協力してくれたことが、推進力につながっているのだと思います。
もちろん、全員が最初からkintone活用に前向きだったわけではありません。
しかし、業者が作ったアプリに働き方を合わせるよりも、自分たちの意見を盛り込んでアプリを作る方が、反発は少ないと思います。
IT化が順調に進んでいるもう1つの理由として、私以外にもkintone担当者がいることが挙げられます。
kintone活用に限ったことではありませんが、新しいことに挑戦するマインドがあって、そのうえで適切な教育をしていく、ということも重要だと思います。
担当者が増えたおかげで、アプリの構築・連携を分担できたので、活用スピードが上がりました。
運用や構築で苦労した点はありますか?
kintone構築で苦労したのは、プラグインの理解です。
私たちがやりたいことは、kintoneの標準機能ではできないことも多く、無料・有料を含めて、どのプラグインを選べば良いのかというところは難しかったですね。
ある程度は動画で調べましたが、費用対効果を踏まえた判断は難しいですし。
この点については、コムデックさんの伴走支援が無かったらと思うと、ゾッとします。
運用面については、「いかに日常業務の延長上にkintoneを置くか」という点に苦労しました。
これまでは、不便に慣れてしまっていた部分もありますが、移行する際に少し大変な思いをしてでも、長期的に見て効率的な方法を取り入れていきたいなと考えています。
社内の課題をITで変えたいなら、どんな会社でも力になってくれると思います
コムデックの伴走支援は御社にとってどのようなメリットがありましたか?
コムデックさんの伴走支援のおかげで、アプリ構築の質やスピードが上がりました。
確か、キックオフをしたのが2024年の2月だったと思うのですが、そこから4月には仮運用、6月には本格運用というスピードで進んでいきました。
もちろん、スピードだけでなく内容も充実していて、当初の課題も解決できました。
具体的には、製造現場にモニターを設置し、情報共有や進捗管理ができるようになっています。
また、受注管理から請求管理も、kintoneで一元管理できるようになりました。
その他の情報も全てアプリで管理しているので、必要なときにすぐに呼び出せるようになったことがメリットです。
担当チームの支援で印象的なのはどんなところでしたか?
印象的だったのは、当社のアプリ構築があのkintone芸人の動画になったことですね。
いつも見ていたkintone芸人さんが「いい事例だな」と言ってくれているのを見て、嬉しかったです。笑
あとは、弊社が東京、コムデックさんが三重県の会社ということで距離があるのですが、東京出張のタイミングで訪問していただけたのも良かったなと思います。
普段はWEB会議で画面越しのやりとりが中心ですが、やはり実際に足を運んで、製造現場も見ていただいたことで、その後のご相談もしやすくなったなと感じます。
また、タイミングが合えば是非来ていただきたいです。
コムデックのサービスはどのような企業に合うと思いますか。
社内の課題を解決したい、IT活用で社内環境を改善したいと考える企業なら、どんな企業でもコムデックさんが力になってくれると信じています。
次はAI活用にも挑戦したいですね
今後はコムデックとどのような課題を解決して、どのような会社にしていきたいですか?
いま解決したいのは、kintoneの容量問題です。
アプリ内で図面のPDFを添付するのですが、現状では各アプリにうまくリンクを飛ばせていません。
今のペースで行くと、あと3年ぐらいで容量の上限に達してしまいそうなので、それまでにコムデックさんと相談しながら、何とかしたいなと思っています。
また、AI活用にも興味はあるのですが、まだ具体的な活用法がイメージできていない状態です。
同じものを大量生産するような製造業の会社であれば、業務フローもシステム化されていてAIが使いやすいのかもしれないのですが、うちのようにオーダーに基づいて製造する会社では、臨機応変に対応することも多いので、なかなか難しいなと感じています。
私はkintone芸人のAI活用動画も毎回チェックしているので、そちらも参考にしながら活用法を模索したいです。
担当者より

担当者:佐田
株式会社松村製作所さまは、当初からkintoneの基本操作をマスターされていたため、環境構築よりも「構築方法をお伝えする」という点に注力しました。
最も苦労したのはプラグインの選定です。
kintoneの標準機能ではできない要件に対して、費用対効果も考えながら最適なものをご提案しました。
また、社長をはじめkintone活用にとても積極的な姿勢でいらっしゃったので、「教える」ではなく「一緒に考える」というスタンスを大切にして、同じ目線でコミュニケーションを取ることも、心がけました。
今後も、株式会社松村製作所さまの意識の高さや社内の協力体制といった強みが活かせるよう、継続的にお手伝いしていきたいと思います。
関連記事
ARTICLE
-
kintoneの『テーブルコピー』を条件分岐処理プラグインでスマホ対応化|株式会社松村製作所さまのアプリ開発事例
-
条件分岐処理プラグイン応用編!アプリ間更新でkintoneの入力を効率化|株式会社松村製作所さまのアプリ開発事例
セミナー/講演会
SEMINAR